
今回は
というテーマでお送りします。
今回は メソッド編の最終回です。
これまでの学習でメソッドの便利さを実感できたかたも
多いことと思います。
確実に前進していますね。
素晴らしいと思います。
そして最終回の今回、メインメソッドに
引数を渡す場合のお話 をしますね。



【Youtube版】
Youtubeでもお伝えしていますので
是非チェックしてくださいね。
【1】 引数の渡し方

ここまで勉強してきて…
メインメソッドにも String型配列の仮引数 args がある事に
気づいたかたも多いと思います。
:
:

これって、どうやって使われるんですか?

最初に実行するメソッドだから…
JVMが考えて、引数を渡すんでしょうか…?

JVMは、そこまで気が利かないと思うけど…。

2人とも、いい線いってますよ…。
メインメソッドの引数は、私たちが java プログラムを
起動する時に「追加情報」を渡すものです。
これをコマンドライン引数といいます。
java コマンドで プログラムを起動する場合には
指定した クラス名 の後に コマンドライン引数を書きます。
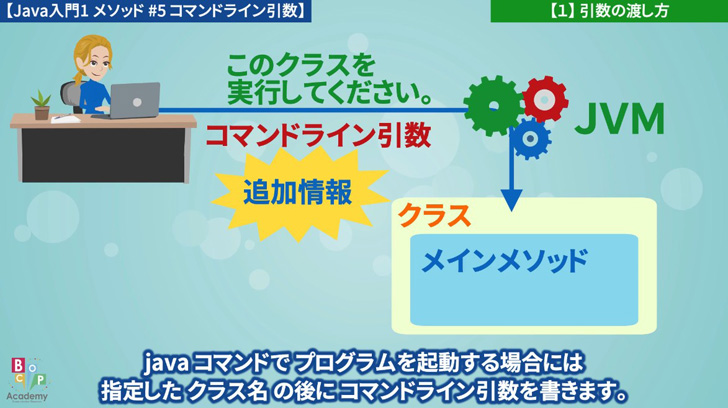
すると、JVMが String型配列にして
メインメソッドに渡してくれます。
例えば、”河合”、”速水” という2つの引数を渡したい場合…
という形で指定します。


コマンドライン引数を指定する場合には
クラス名の後、引数と引数の間はスペースで区切ります。
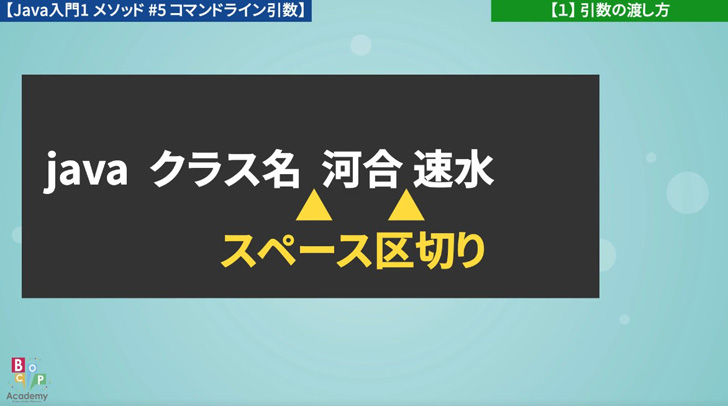
そして、このように起動すると、JVMは以下の順に行います。
❷ 参照値(番地の情報)の配列を作成する。
❸ 作成した配列の参照値をメインメソッドの仮引数 args に設定する。
❹ メインメソッドを起動する。
するとメソッド側は
仮引数 args[0] で “河合” を使えて…
args[1] で “速水” を使える事となるのです。
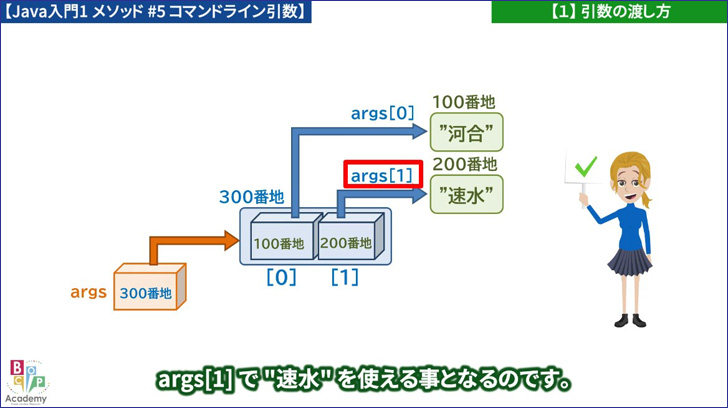
【2】 要素数

コマンドライン引数は String型配列 args で渡されますが
この args の要素数は、実行時に決まります。
クラス名の後に、何も書かなければ 0 個、1つ書けば 1 個
2つ書けば 2 個…というようになります。
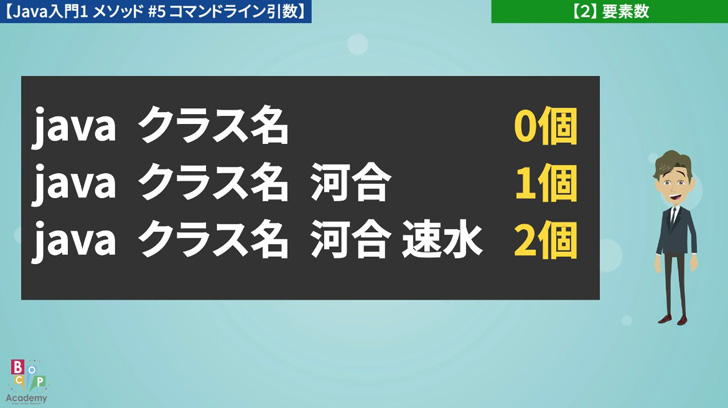
配列の要素数は、Java超入門で勉強した通り…
配列名.length で取得できましたね。
プログラムの中で、要素数を確認して処理したい場合には
この値を参照するようにしましょう。

スッキリ感があります。

とっても便利に使えそうですね。
また、演習問題をやります。
【まとめ】

java プログラムを起動する時に
追加情報を渡すもの。
・コマンドライン引数という。
・java コマンド実行時に
クラス名の後に スペース区切りで
記述する。
・String型配列として渡される。
実行時に決まる。
・配列要素数は、以下で取得できる。
配列名.length

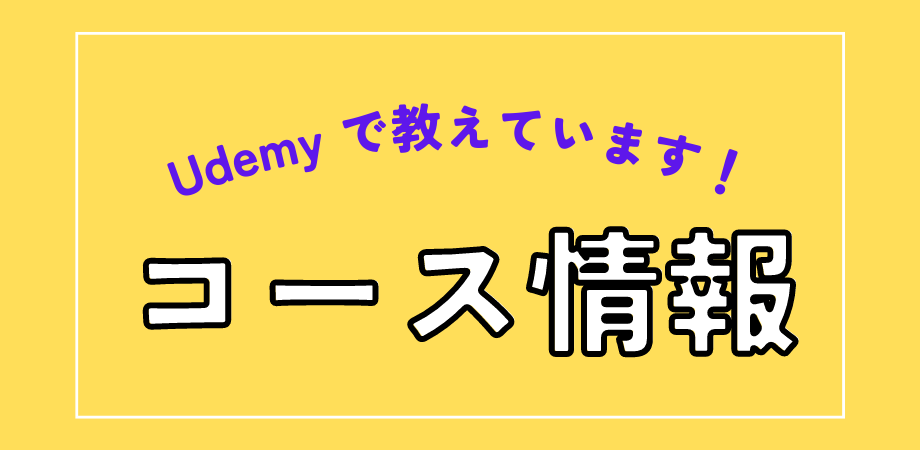







今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。