
今回は
というテーマでお送りします。
メソッドの「引数」で配列を渡す場合と
「戻り値」を配列にする場合を見ていきましょう。

よろしくお願いします。

全集中でいきます!

【Youtube版】
Youtubeでもお伝えしていますので
是非チェックしてくださいね。
【1】引数が「配列」
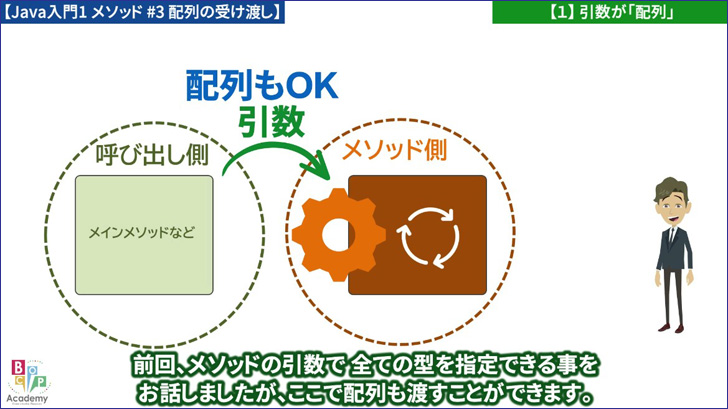
前回、メソッドの引数で 全ての型を指定できる事を
お話しましたが、ここで配列も渡すことができます。
メソッド側では、仮引数に
を指定します。
呼び出し側では、実引数に 配列名を指定します。
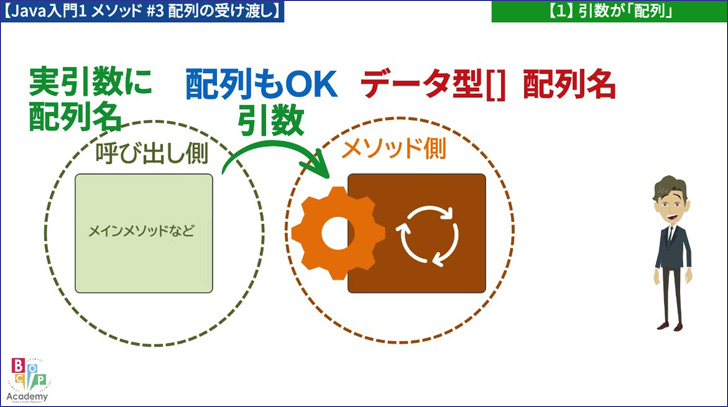
int[] a = { 10, 20, 30 };
displayArray( a );
// メソッド側
static void displayArray( int[] array ) {
for (int i = 0; i < array.length; i++) {
System.out.println(array[i]);
}
}
この例では、メソッド側は int型配列の array という
仮引数を受け取って、メソッド内で表示処理に使っています。
仮引数の型の記述は int[] となっていて
少し混乱してしまうかもしれませんが…。
int[] ここまでで、配列の型を表す!
…と区切って考えましょう。
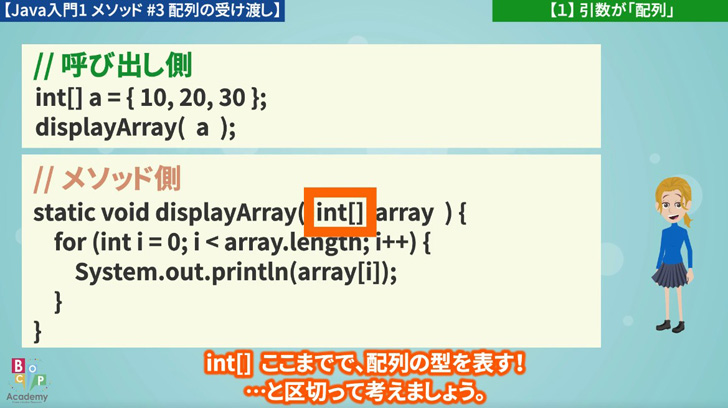
呼び出し側では、int型配列 a を宣言・初期化した後に
a を実引数として メソッドに渡しています。
こちらは、配列名を書くだけでOKです。
【2】戻り値が「配列」
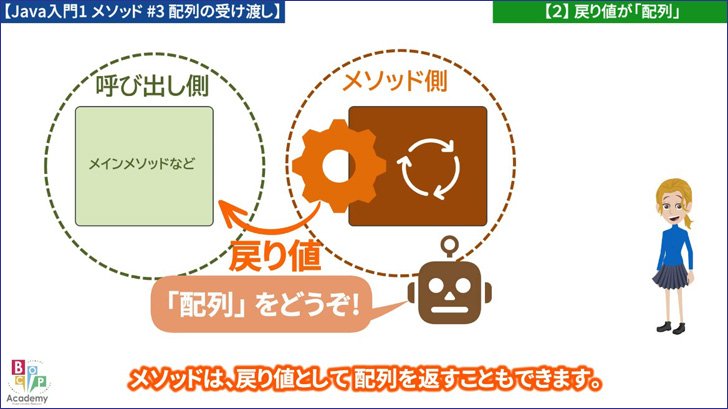
メソッドは、戻り値として
配列を返すこともできます。
メソッド側では、戻り値の型として
を指定します。
そして return の右側に書く戻り値には
配列名を記述する事となります。
呼び出し側は、メソッドを呼び出して戻ってきた時に
呼び出し部分が 結果の配列に置き換わります。
配列を宣言して代入するなどして
使用する事ができます。
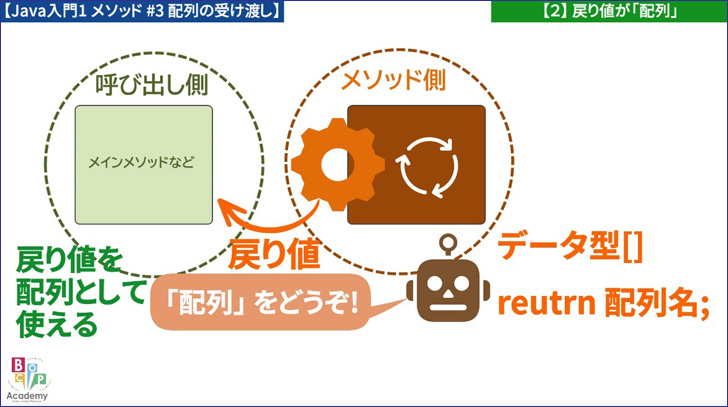
int[] a = getArray();
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
System.out.println(a[i]);
}
// メソッド側
static int[] getArray() {
int[] array = {10, 20, 30};
return array;
}
この例を見てみましょう。
まず、メソッド側は メソッド名は getArray で
仮引数は ありません。
戻り値を見ると int[] となっていて
int型配列 であると分かります。
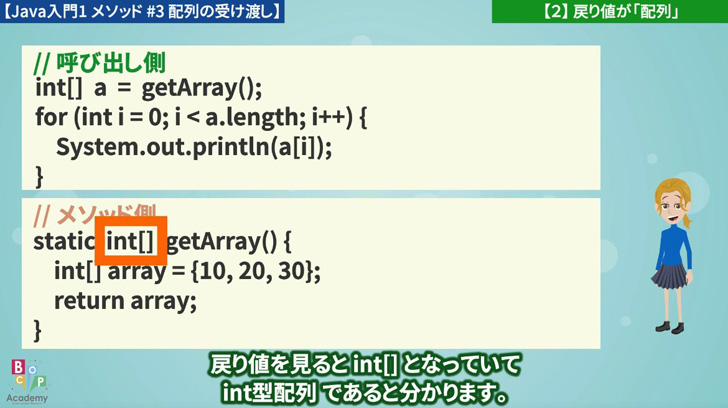
この部分も、最初に見ると少し
違和感があるかも知れませんが…
int[] このセットで、配列の型とみるようにしましょう。
メソッドの中では、int型配列を宣言して
{ 10, 20, 30 } で初期化しています。
そして、宣言した配列を戻り値としてリターンしています。
このように、配列名 を記述すればOKです。
呼び出し側は、int型配列 a を宣言して
初期化しています。
ここで、メソッド getArray を呼び出すと
その戻り値で配列が返ってくるので a に代入できるのです。
そのまま a は、int型配列として使用できますので
この for 文によって …
20
30
と表示される事となります。

意味で捉えれば理解できそうです。
演習問題に取り組みます。

受け渡せるので便利に感じました。
活用していきます!
【まとめ】

● メソッドでの 配列 の受け渡し
配列を渡すことができる。
・メソッド側では、仮引数に
以下のように記述する。
データ型[] 配列名
・呼び出し側では、実引数に
配列名を指定する。
配列を返すことができる。
・メソッド側では、戻り値の型を
以下のように指定する。
データ型[]
・returnの右の戻り値には
宣言した配列名を記述する。

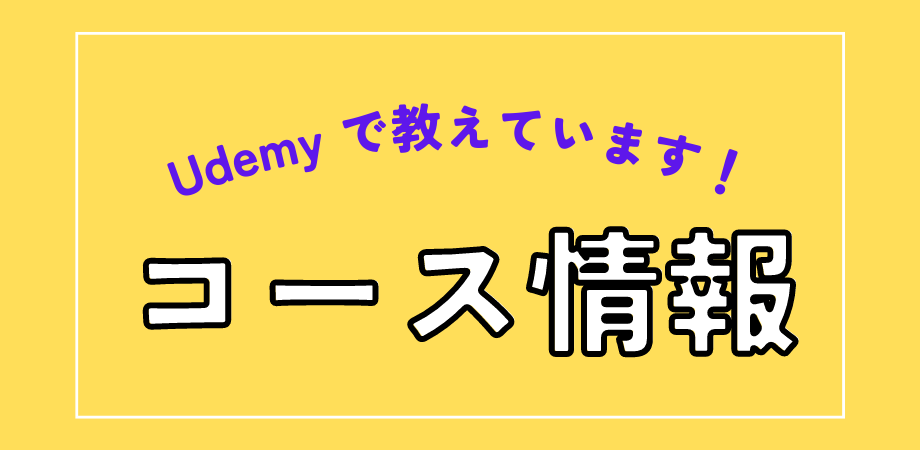







今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。