
今回は
というテーマでお送りします。

分かってきました。
今回も、新たな事を学ぶのが楽しみです。
よろしくお願いします。

とても面白いと思いました。
用語も たくさん出てきていますが
今回も、ガッツリ頑張ります。
【1】 コンストラクタ

設計図となるクラスには、2つのメンバ
フィールド と メソッド を定義するとお伝えしました。
そして今回は、もう1つのメンバを見ていきましょう。
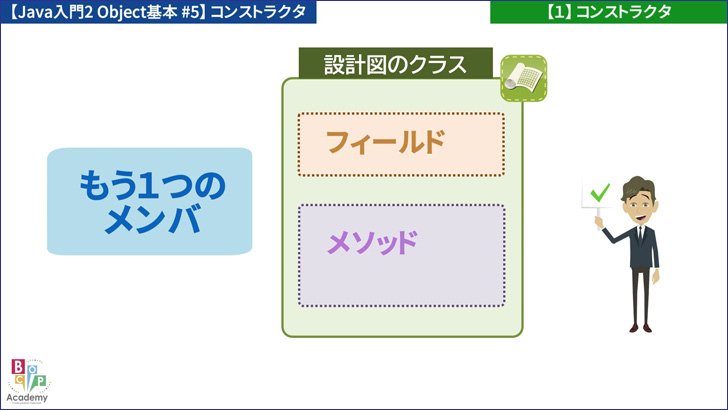
コンストラクタというもので
クラスが インスタンス化される時に
実行されるメンバです。
実行されるメンバ。
コンストラクタの中には、フィールドの初期化など
インスタンス化される時に 実行したい処理を記述します。
コンストラクタは、Javaソースファイル中で
一般的に、このように配置されます。
1つの Javaソースファイルの中に
クラスを 1つ 記述して
まずは、フィールドを記述します。
その次に、コンストラクタを記述して。
その後に、メソッドを記述することとなります。
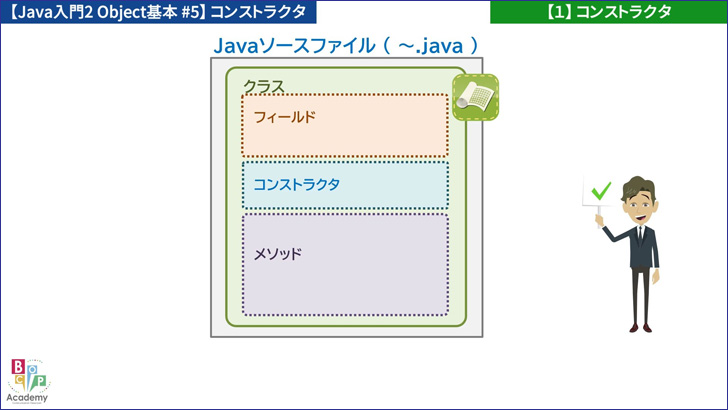
ここでは、Javaのクラスの中での 3つのメンバの配置を
ザックリ 押さえておきましょう。
【2】 コンストラクタ定義

コンストラクタはこのように定義します。
処理ブロック
}

メソッドの「いとこ」みたいな感じですか…?

メソッドの 「 いとこ 」 かどうかは分かりませんが…
仮引数を受け取れるところや、処理を行うブロックが
あるところは メソッドに似ていますね…。
ただ、普通のメソッドとは、このような違いがあります。
❷ 戻り値なし。
❸ 実行されるのはインスタンス化される時。
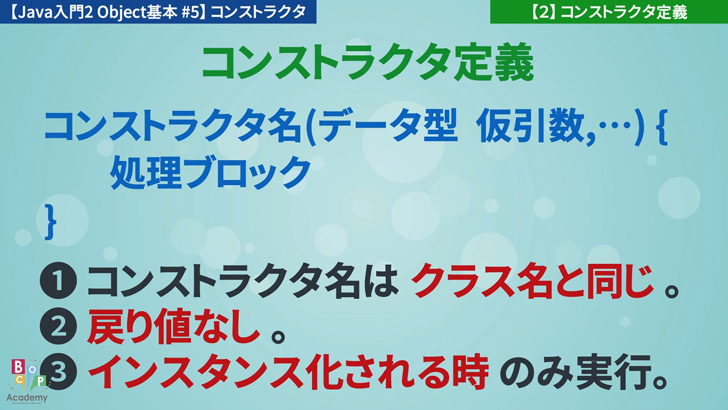
【例】を見てみましょう。
前回に引き続き、営業部員を表す SalesEmployee クラスです。
String name;
int salesAmt;
SalesEmployee(String n, int a) {
name = n;
salesAmt = a;
}
// この後にメソッド…
}
クラスの中で
最初にフィールドが、2つ定義されています。
名前を表す String型変数の name と
売上合計金額を表す int型変数の salesAmt です。
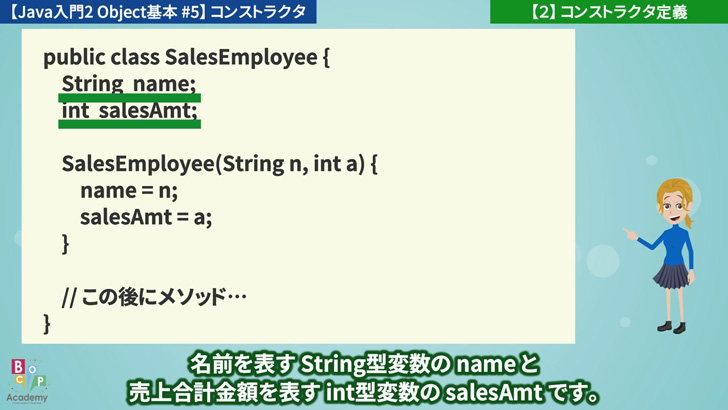
そして、その次にコンストラクターの記述です。
コンストラクタ名 SalesEmployee は クラス名と
同じですね。
仮引数を2つ受け取っています。
フィールドを初期化するための…
名前を表す String型引数の n と
売上合計金額を表す int型引数の a です。
戻り値はありません。戻り値の型 void も書きません。
そして処理ブロックの中では、フィールドの値の
初期化を行っています。
フィールド name に 引数 n を代入して
フィールド salesAmt に 引数 a を代入しています。
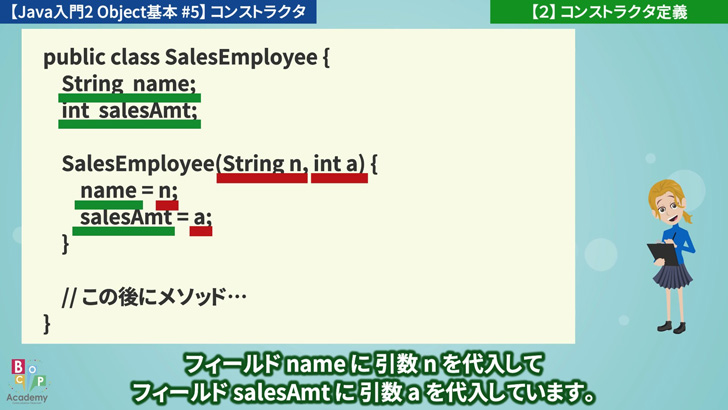
このように、フィールドの初期化などが
行われる場合が多いものです。

書かなかったんですが…。
コンストラクタは、無くてもいいんですか?

Goodですよ~。
そして、答えですが…
デフォルトコンストラクタ というものがあります。
これは…
クラスにコンストラクタの記述がない場合に
Javaで暗黙的に付加されるものです。
そして、「引数なし」「中身が空(処理なし)」の
コンストラクタです。
Javaで暗黙的に付加される。
・ 「引数なし」「中身が空(処理なし)」の
コンストラクタ。
前回の例では、SalesEmployeeクラスに
フィールド と メソッド だけを定義したので…
String name;
int salesAmt;
SalesEmployee() {
}
// この後にメソッド…
}
このように、Javaが 暗黙的に
デフォルトコンストラクタを 付加していたのです。
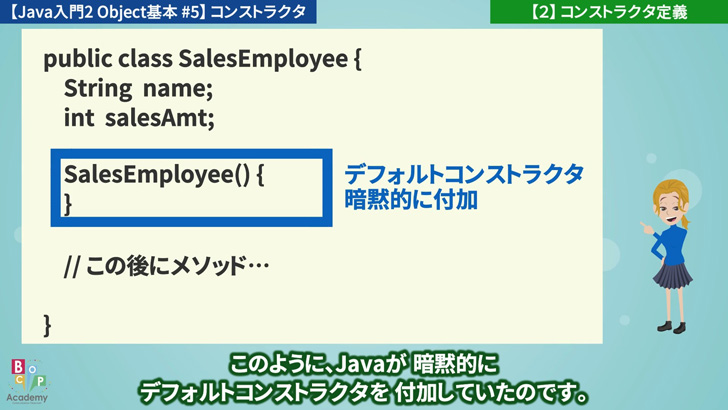
そして、1点 注意点があります。
この デフォルトコンストラクタは
コンストラクタが記述されていない場合に 付加されるもので…
実際に、コンストラクタが 記述された場合には
付加されないという事です。
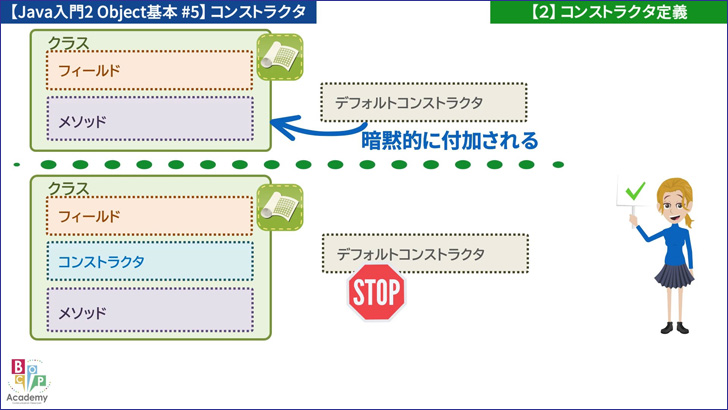
この部分も、押さえておきましょう。
【3】 this.

this キーワードについて、見ていきましょう。
この this は、自身のインスタンスを
指し示すキーワードです。
この this の後に
ドット演算子とメンバ名を指定することで…
明示的に、自身のインスタンスのメンバに
アクセスすることが できます。
明示的に、自身のインスタンスの
フィールドにアクセスできます。
また
this.メソッド名(実引数,…) と書くと…
明示的に自身のインスタンスの
メソッドにアクセスできます。
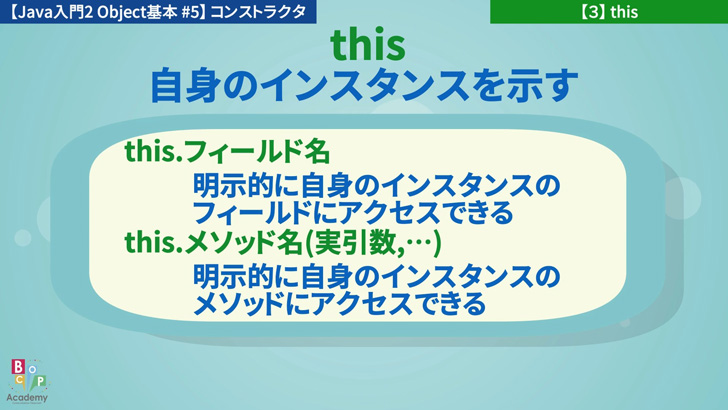
例を 見てみましょう。
String name;
int salesAmt;
SalesEmployee(String name, int salesAmt) {
this.name = name;
this.salesAmt = salesAmt;
}
// この後にメソッド…
}
前のコーナーと同じ例ですが…
フィールド名は、name と salesAmt です。
そして、コンストラクタの仮引数名も
同じ name と salesAmt にした場合です。
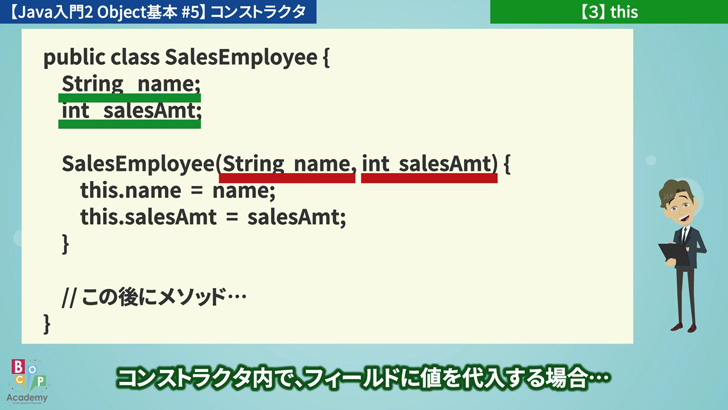
コンストラクタ内で、フィールドに値を代入する場合…
this.name = name;
this.salesAmt =salesAmt;
と記述します。
左辺の this.フィールド名 で、自インスタンスの
フィールドを明示的に表しています。
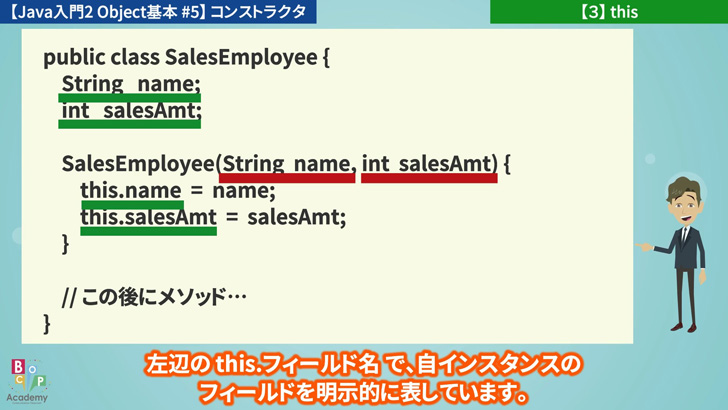


Goodです。
String name;
int salesAmt;
SalesEmployee(String name, int salesAmt) {
name = name;
salesAmt = salesAmt;
}
// この後にメソッド…
}
このように書いた場合ですね…。
フィールドのスコープは、クラス全体です。
仮引数のスコープは、コンストラクタ内です。
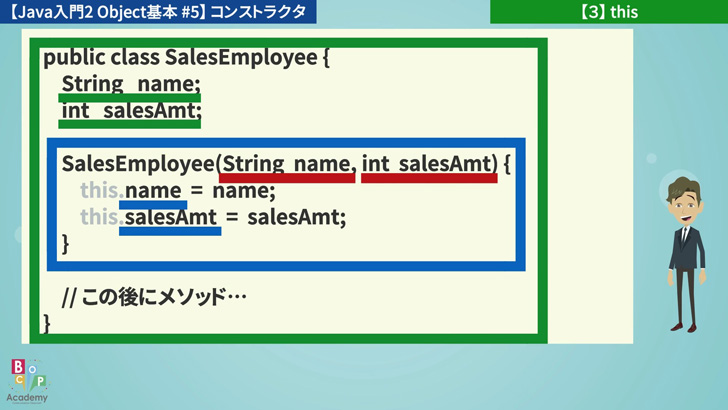
コンストラクタ内では、フィールド name も仮引数 name も
どちらも スコープですが…
このように 変数名が重複している場合には
内側の(狭い)範囲で 宣言されている 変数 を指します。
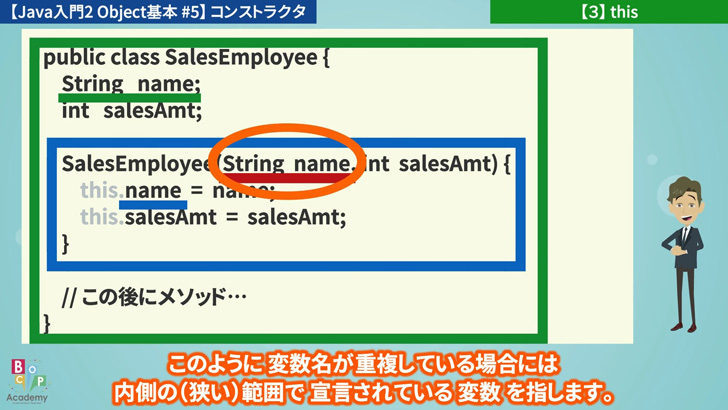
ですので、この場合には…
仮引数 name に 仮引数 name の値を代入し…
仮引数 salesAmt に 仮引数 salesAmt の値を
代入することになってしまいます。
つまり、フィールドに値を設定しない事に
なってしまうのです。
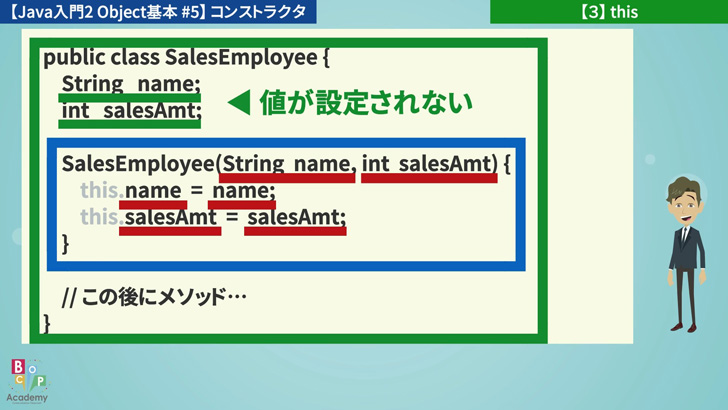
ですので、左辺は 自身のインスタンスの
フィールドと明示するために…
this をつける事が 必須になるのです。

this をつけなくて 大丈夫ですか?

前のコーナーの例のように…
仮引数名を変えれば、this をつけなくても大丈夫です。
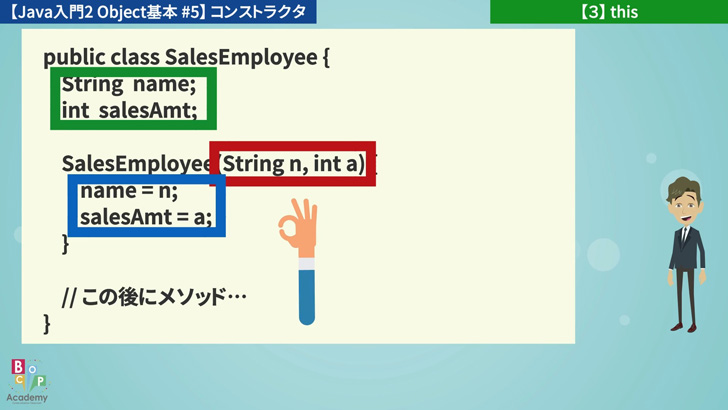
ただし、同じ項目を表す場合に 同じ名前をつける事が…
分かりやすさの面でも 多く使われます。
また、eclipseなどツールで
コンストラクタやメソッドを自動生成する時にも…
同じ項目には 同じ名前がつけられる
パターンが多いものです。
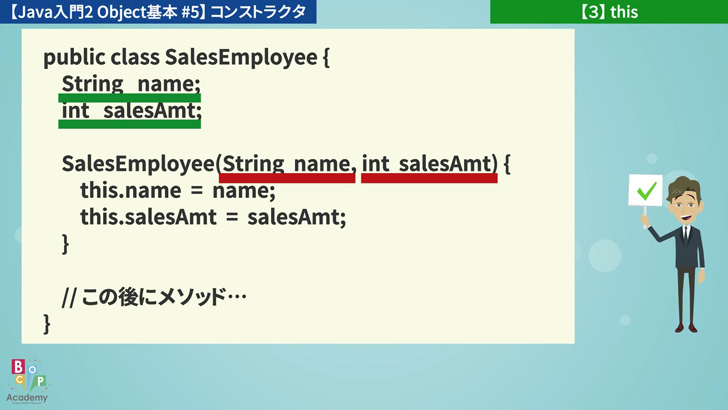
ですので、この部分は
ぜひ押さえておいてくださいね。
【4】 インスタンス化

クラスから実体のオブジェクトを作成することを
インスタンス化といいますが…
このインスタンス化は
① new演算子を用いてメモリ領域を確保
して…
② コンストラクタを実行
することで実現します。
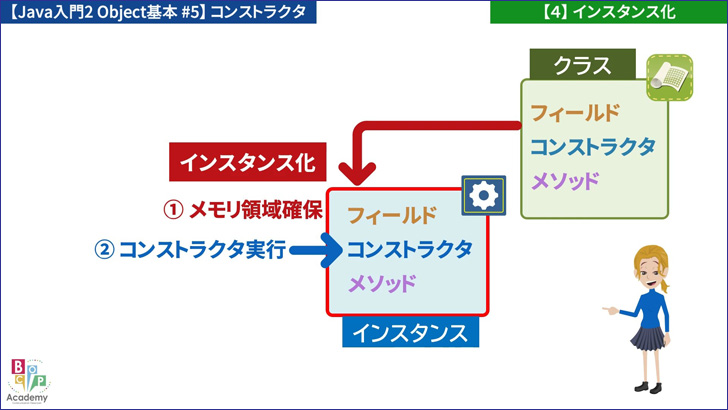
② コンストラクタを実行
そして この時、クラスを利用する側では
このように記述する事になります。
※「実引数,…」はコンストラクタへの実引数。
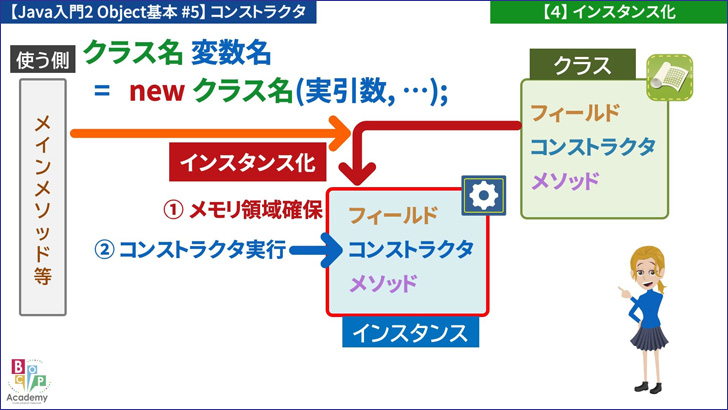
前回 お伝えした時には、この「実引数,…」の部分が
無しだったという事になります。
前回は、クラスの定義の中で
コンストラクタを定義しなかったので…
デフォルトコンストラクタが 暗黙的に付加され
それを 呼び出していたからなんです。
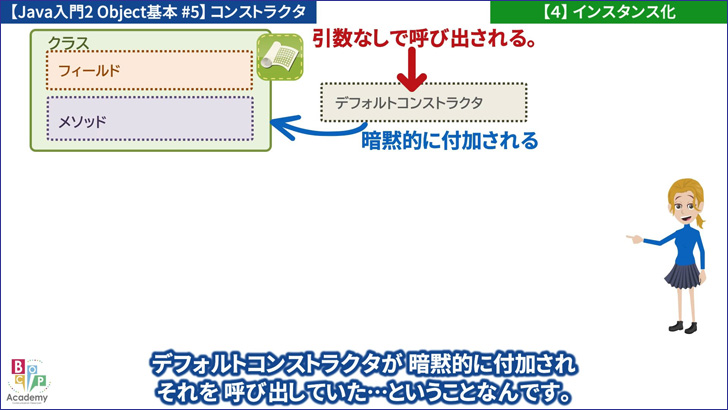
クラスで、仮引数ありの コンストラクタを定義した場合には
その仮引数ありのコンストラクタを 呼び出す事となります。
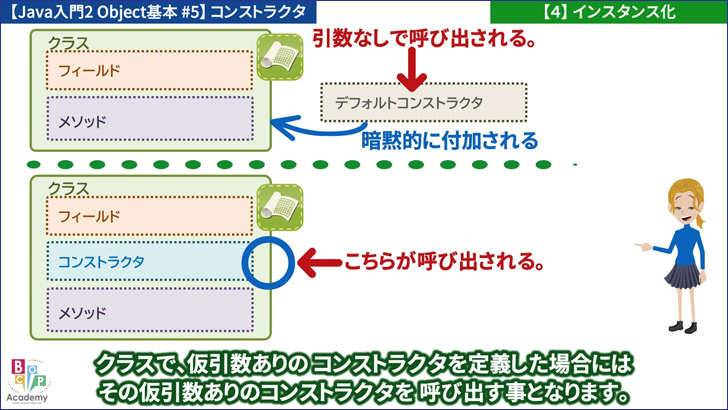
例を 見てみましょう。
String name;
int salesAmt;
SalesEmployee(String name, int salesAmt) {
this.name = name;
this.salesAmt = salesAmt;
}
// この後にメソッド…
}
このクラスを インスタンス化する場合には…
= new SalesEmployee(“速水剛留”, 1000000);
と記述する事になります。
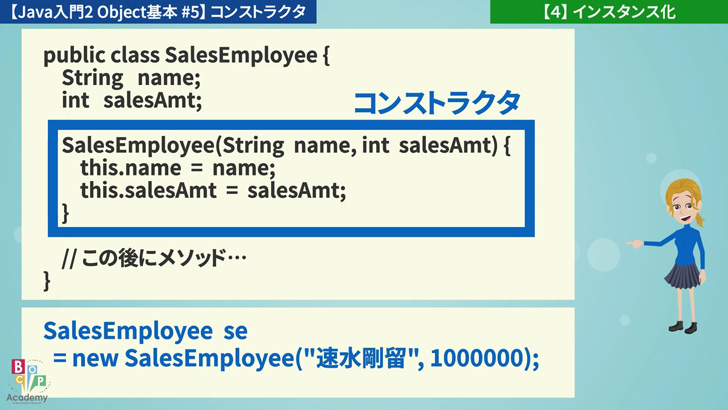
イメージを再確認しておきましょう。
クラスをインスタンス化するときの記述方法は…
クラス名 変数名 = new クラス名(実引数,…);
となります。
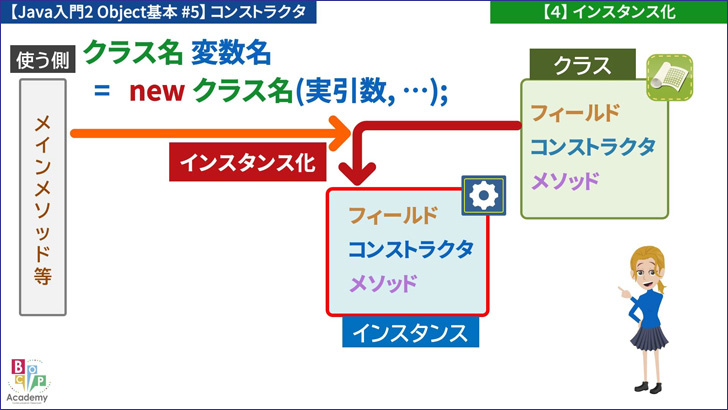
内部的には…
① new演算子を用いてメモリ領域を確保
して…
② コンストラクタを実行
することで実現しています。
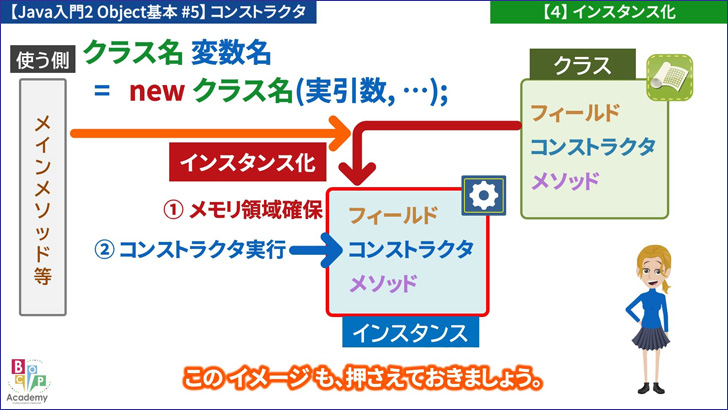
この イメージ も、押さえておきましょう。
【まとめ】
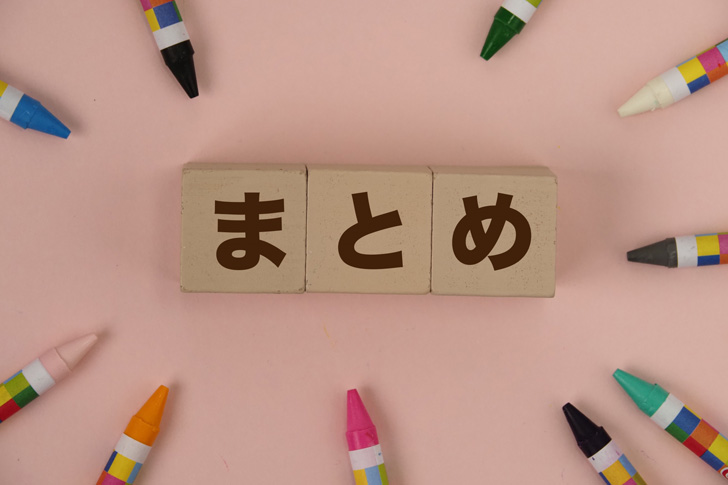
される時に実行されるメンバ。
コンストラクタ名(データ型 仮引数,…) {
処理ブロック
}
・ コンストラクタ名は
クラス名と同じ。
・ 戻り値はなし。
void も書かない。
・ 定義しないと 自動的に
デフォルトコンストラクタが
付加される。
自身のインスタンスを指し示す。
・ this.メンバ で、明示的に
自身のインスタンスの
メンバにアクセスできる。
new クラス名(実引数,…)

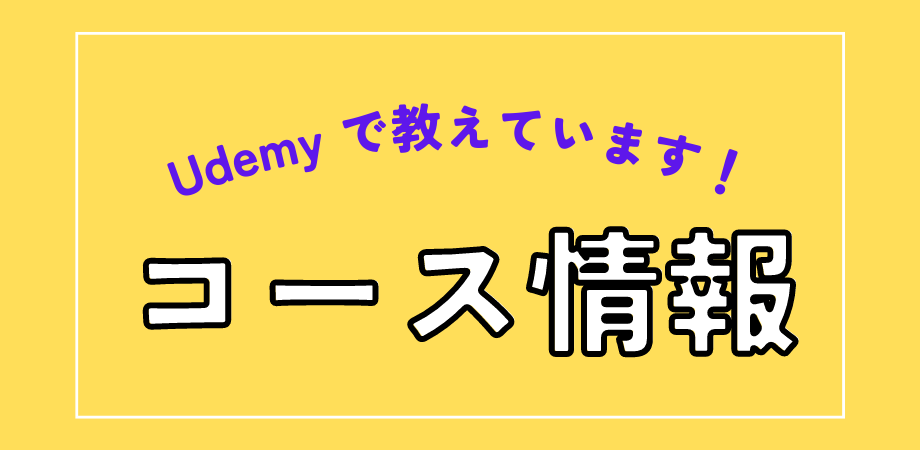









今回も、ご覧いただき、ありがとうございます。